ページ内にはアフィリエイトを利用したリンクが含まれています。
シジウィック
シジウィックと功利主義
ベンサムとミルの功利主義を完成させ、現代功利主義を創始したと言われるのが、イギリスの倫理学者ヘンリー・シジウィック(Henry Sidgwick、1838-1900)である。
実はシジウィックは、最初から功利主義者として功利主義を提唱したわけではない。
彼は『倫理学の諸方法』という著作を著しているが、その主題は、いろいろある道徳的な考え方のなかから有力な考え方を3つ取り上げ、そのうちのどの考え方がもっともすぐれているかについて探究することであった。
つまり、〝行為の善悪を判断する根拠として結局何が正しいのか?〟を突き止めようとしたのである。
その探究の結果、シジウィックがもっとも有力な考え方だとみなしたのが、功利主義なのであった。
『倫理学の諸方法』
シジウィックが『倫理学の諸方法』のなかで取り上げた3つの考え方とは、「倫理的利己主義」(利己的快楽主義)「直観主義」(直覚主義)「普遍的快楽主義」(功利主義)である。
「倫理的利己主義」(利己的快楽主義)とは、行為の善悪を判断する根拠は〝自分自身の幸福〟であるとする考え方である。
この考え方の持ち主は、たとえば、〝相手に好かれたい、だから相手が喜ぶことをする〟〝贅沢な生活がしたい、だから一所懸命働く〟というように、自分の利益のために(結果的に)道徳的だとされる行為を行なう。
次に「直観主義」(直覚主義)とは、行為の善悪を判断する根拠は〝道徳的直観力〟であるとする考え方である。
この立場の人びとは、道徳的な判断というものは、たとえば「道徳感覚」(モラルセンス)や「理性」のような、人間が持つなんらかの〝特殊な能力〟によってもたらされると考える。
最後に「普遍的快楽主義」(功利主義)とは、行為の善悪を判断する根拠は〝行為の影響を受ける関係者全員の幸福〟であるとする考え方である。
この立場の人びとは、行為をするとき、その行為の影響が及ぶ人びと全員のことを考える。
なお、シジウィックが言う「幸福」とは「快楽」と同じ意味であり、快楽の質の違いを重視したミルとは異なり、その量が多いか少ないかだけを問題にした。
実践理性の二元性
シジウィックは、「倫理的利己主義」(利己的快楽主義)「直観主義」(直覚主義)「普遍的快楽主義」(功利主義)という3つの方法を比較検討した。
その結果、特定の価値観に縛られることなく、社会全体の幸福=「一般幸福」という大きな理念の実現をめざし、また科学的で客観的な原理である「普遍的快楽主義」(功利主義)こそがもっとも有力な倫理学の考え方だとみなした。
しかし、その一方で、シジウィックは、個人の幸福の追求と社会の幸福の実現とが一致しない場合、それをどう考えるべきかという問題に突き当たった。
ミルは、利他的に行為しようとする人間性を発達させることによって、個人の幸福の追求と社会の幸福の実現とは一致しうると考えた。
しかし、シジウィックは、そうしたミルの考え方に同意できなかった。
なぜなら、自己犠牲を正当化し、義務化してしまうからである。
〝他人や社会のために何かをすべきである〟という考え方自体は悪いわけではないし、合理的な場合がある。
しかし、個人の幸福の追求(利己心)と社会の幸福の実現(義務)とが一致しないとき、人は個人の幸福のほうを選択することがある。
そして、そうした選択も合理的な場合がある。
このように考えた結果、シジウィックが唱えた概念が「実践理性の二元性」であった。
これは、利己心と義務が衝突する場合、実践理性は分断され、どちらにつくこともしないという考え方である。
つまり、シジウィックは、功利主義の立場をとろうとしたが、「倫理的利己主義」(利己的快楽主義)にも合理性を認め、そのためにどちらも捨て去ることができず、両者を折衷しようとしたのであった。
規則功利主義と行為功利主義
功利主義への批判
功利主義では、社会全体の幸福が増大するような行為が〝善い行為〟だと考える。
しかし、そうすると、〝善い結果〟が重視される一方、道徳的なルールが軽視され、その結果、受け入れがたい判断がもたらされるケースが出てくる可能性がある。
たとえば、臓器移植を受ければ助かる5人を救うために、1人の健康な若者を殺してもよいというような判断である。
功利主義に従えば、こうした判断が肯定されるのではないか――?
規則功利主義
こうした批判への応答として、アメリカの倫理学者リチャード・ブラント(Richard Brandt、1910-1997)らが提唱したのが、「規則功利主義」(rule-utilitarianism)である。
つまり、「功利性の原理」を「行為」に適用するのではなく、「規則」に適用するという考え方である。
上述の例で言えば、若者を殺せば5人の命が助かるとしても、その行為によって〝人を殺してはならない〟という規則が信頼を失い、社会全体の幸福を減少させることになる。
また、〝人を殺してはならない〟という規則を守るほうが、社会全体の幸福を増大させることになる。
よって、「功利性の原理」を「規則」に適用するのがふさわしい――
「規則功利主義」の立場に立てば、そのように考えることができるのである。
行為功利主義
「功利性の原理」を「行為」に適用する従来の立場を「行為功利主義」(act-utilitarianism)と呼ぶ。
「行為功利主義」は、「規則功利主義」に対して、規則が複雑になれば結局のところ「行為功利主義」と同じになるのではないか、あるいは、規則にこだわると人びとが不幸になっても、それを見過ごしてしまい、結局は功利主義の基本精神に反することになるのではないか、といった批判を投げかけている。
ヘア
二層理論
〝功利主義は5人の命を救うために1人を犠牲にすることを容認する〟というような批判がある。
この批判は、人びとの常識的な道徳=「直観」にもとづいている。
つまり、ふつうの人びとの感覚からすれば、〝ありえない道徳的な判断〟だというわけである。
イギリスの哲学者・倫理学者で、『道徳の言語』『自由と理性』『道徳的に考えること』などの著作を遺したリチャード・マーヴィン・ヘア(Richard Mervyn Hare、1919-2002)は、こうした「直観」による批判は、道徳的な判断における2つのレベルを混同していると考えた。
ヘアは、道徳的な判断を「直観的レベル」と「批判的レベル」という2つのレベルに分けた。
「直観的レベル」とは、日常的に直面するさまざまな状況に対して、不充分な情報しかないなかで、複数の道徳原則のいずれかにもとづき、即座に道徳的な判断をするレベルである。
一方の「批判的レベル」とは、道徳原則に疑問が生じたり、道徳原則のあいだに対立や混乱が生じたりしたとき、時間をかけて情報を集め、道徳原則を検討するレベルである。
つまり、ヘアによれば、人は通常、たとえば〝人には親切にするべきである〟というような道徳原則にもとづいて直観的な判断を行なっているが、一方で、たとえば〝人を傷つけてはならない〟〝他人を助けるべきだ〟といった複数の道徳原則が対立するような状況においては、道徳原則を批判的に検討したうえで判断するのだという。
こうしたヘアの考え方を「二層理論」と呼ぶ。
そして、「二層理論」に従えば、〝功利主義は5人の命を救うために1人を犠牲にすることを容認する〟という批判は、「批判的レベル」の問題を、「直観的レベル」の問題として誤って扱うことから起きるのである。
また、「二層理論」に従えば、人びとは、日常生活においては、「規則功利主義」的に道徳原則に従うが、複数の道徳原則が対立した場合には、「行為功利主義」的に関係者全員の幸福を最大化する行為を選ぶと考えることができる。
このようにして、ヘアは、「規則功利主義」と「行為功利主義」の対立を調停したのであった。
指令性と普遍化可能性
ヘアは、「二層理論」を唱えた一方で、道徳的な判断の際に使われる言葉がどのような性質を備えているかについて考察し、功利主義を新しい方向へ展開させた。
私たちはよく〝~すべきである〟と言う。
たとえば、あなたがAさんに向かって〝人には親切にすべきである〟と言ったとする。
そして、Aさんがあなたの言葉を受け容れたとする。
ヘアによれば、このときAさんは同時に、〝人には親切にすべきである〟と言ったあなたの指令(命令)も受け容れたのである。
つまり、この「べき」という言葉のなかには「~せよ」という指令の意味が含まれているのであり、道徳的な言葉が持つ基本的な働きは、聞き手に行為を指令することにあるのだという。
道徳の言葉がもつこうした性質を、ヘアは「指令性」と呼んだ。
さらに、ヘアは、「べき」という道徳の言葉のもうひとつの性質について指摘した。
たとえば、ある状況において、あなたはAさんに〝ウソをつくべきではない〟と言ったとする。
そして、またあるとき、あなたとAさんは、ほぼ同じような状況に直面したとする。
このとき、あなたは、Aさんに対して、やはり〝ウソをつくべきではない〟と言うはずだ。
つまり、ヘアによれば、ある状況においてある道徳的な判断を下すということは、他の同じような状況においても同じ判断を下すことを意味するのである。
また、このことは、もしもあなたがAさんとまるで同じ立場にあるならば、同じ判断が自分自身にも下されるべきだという見解を受け容れることにつながる。
なぜならば、Aさんが置かれていた同じ立場に自分が置かれたとき、Aさんに対して指令したことを、自分は受け容れないというのは、明らかに矛盾しているからである。
ヘアはそう考え、道徳の言葉がもつこうした性質を「普遍化可能性」と呼んだ。
選好功利主義
ところで、ヘアによれば、道徳的な判断に「指令性」という性質があるならば、そうした判断をする人は、自分自身で、その指令に同意しているという。
つまり、その指令によってもたらされる状況の実現を、他の状況の実現よりも望んでいるからこそ、そうした指令を発するのだという。
こうした望みを、ヘアは「選好」と呼んだ。
そして、人びとの道徳的な判断の根源にある「選好」が「普遍化可能性」と両立するように最大限に充足されることが、道徳的に〝善い〟と考えた。
こうしたヘアの考え方を「選好功利主義」と呼ぶ。
このようにしてヘアは、ベンサム以降の功利主義が行為の善悪の基準としてきた「快楽」や「幸福」の実現を「選好の充足」へと置き換えたのであった。
シンガーの「動物解放論」
なお、ヘアの教え子で、現代を代表する倫理学者にピーター・シンガー(Peter Singer、1946-)がいる。
シンガーは、「選好功利主義」の立場から、主に生命倫理の問題を扱い、大きな影響を与えた。
特に、現代の動物利用のあり方を考察した「動物解放論」は、シンガーのもっともすぐれた哲学的功績だと言われている。
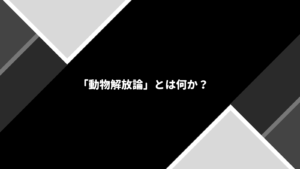
アンスコム
ソクラテス、プラトン、アリストテレスの倫理学においては徳に関する考察が重視されたが、近代において徳に関する目立った考察は行なわれなかった。
その代わりに、道徳に関する議論は「義務」や「権利」が中心となり、〝どのような行為をなすべきか?〟が問題とされた。
しかし、20世紀後半になると、アリストテレスが唱えた倫理的な概念を現代に復活させようという動きが起こり、そこでは〝どのような(徳を備えた)人間になるべきか?〟が問題とされた。
この動きの先駆者は、イギリスの哲学者ガートルード・エリザベス・マーガレット・アンスコム(Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe、1919/3/18-2001/1/5)であった。
彼女は1958年、「現代の道徳哲学」(Modern Moral Philosophy)という論文を発表した。
このなかで、〝カントの義務論は道徳法則の「立法者」(=神)の存在を前提にしているが、いまや多くの人びとは神を信じておらず、よって「立法者」を前提することや、その「立法者」に由来する「義務」を想定することは無意味である〟と述べた。
また、義務論とは対照的な功利主義に代表される、〝ある行為の結果(帰結)がよければ、その行為は道徳的である〟という「帰結主義」(consequentialism)をも批判した。
そして、倫理学の主題となるべきなのは、「義務」でも「帰結」でもなく、アリストテレスが唱えた「幸福」(エウダイモニア)を実現する「徳」(アレテー)なのであって、そのためには心理学の哲学によって「行為」「意図」「快」「欲求」といった概念を解明し、行為者の意図や行為者自身による行為の位置づけなど、どれだけ行為者がよく考えて行為したかを重視することが必要である――
そうアンスコムは唱えたのであった。
マッキンタイア
美徳なき時代
アメリカ合衆国の哲学者アラスデア・マッキンタイア(Alasdair MacIntyre、1929/1/12-)は、『美徳なき時代』において、近現代の倫理学を批判し、主にアリストテレスの倫理思想を再評価した。
マッキンタイアによれば、現代は、道徳の絶対的な根拠を失い、道徳が崩壊した「美徳なき時代」である。
その結果、あらゆる道徳判断は、態度や感情の表現だとみなされるようになった。
マッキンタイアは、こうした立場を「情緒主義」と呼ぶ。
それでは、なぜ「情緒主義」が蔓延するようになったのか?
それは、「啓蒙主義」が失敗したからだという。
マッキンタイアが言う「啓蒙主義」とは、道徳を合理的に説明しようとする立場のことである。
しかし、カントが「理性」、キルケゴールが個人の「選択」、ヒュームが「情念」だと唱えた道徳の根拠は並立するものではなかった。
そのため、そうした学説を根本から合理的に説明しようとする「啓蒙主義」の試みは失敗に終わる。
さらには、「有神論」が崩壊し、神の存在そのものを疑う思潮が広がった。
そのため、「情緒主義」が蔓延したのだという。
共同体と共通善
こうした状況を打開するためにマッキンタイアが注目したのは、「共同体」であった。
「情緒主義」は〝快〟をもたらしたり〝有用〟であったりする行為を道徳的な行為だと考えたが、実は〝快〟や〝有用〟だと感じるその感じ方は「共同体」のなかで身につけたものだ。
つまり、個人は、「情緒主義」が考えたような独立した個ではなく、「共同体」のなかに埋め込まれた存在なのである。
ここでマッキンタイアは、ポリス(古代ギリシアの都市国家)における人間の〝善き生〟を考察したアリストテレスの倫理思想を復活させようとする。
つまり、共同体の目的(「テロス」)に沿う〝共同体全体にとっての善〟=「共通善」をもたらす徳を身につけなければならないと唱えたのである。
共同体主義
「共通善」をもたらすためにマッキンタイアが注目したのが、「実践」「物語的秩序」「伝統」であった。
なかでも最重要だとされたのが「実践」だ。
たとえば、チェスというゲームでうまくプレーする(「実践」する)には集中力と想像力(という徳)が必要だが、集中力と想像力は、その集中力と想像力を必要とするチェスをプレーしないと身につかない。
つまり、徳と「実践」は不可分なのであり、だから「実践」は最重要なのであった。
一方、共同体の目的と歴史という「物語的秩序」があるからこそ、人は役割を自覚し、社会的責任を果たすことができる。
また、共同体の成員は、共同体の存続のために、前の世代から受け継いだものを次の世代へ受け渡す役割を担うが、そのためには「伝統」を重んじなければならない。
歴史的に形成されてきた共同体の伝統のなかで生きるための徳に注目したマッキンタイアの考え方は「共同体主義」(コミュニタリアニズム)と呼ばれ、現代倫理学に大きな影響を与えている。
フット
道徳の根拠は自然本性
ソクラテス、プラトン、アリストテレス、アンスコム、マッキンタイアにおいて明らかだったように、徳を重視する倫理学=徳倫理学においては、道徳の根拠を、行為の動機や結果に求めるのではなく、人間の特性や性格に求める。
つまり、〝善い行為〟とは〝善い人間がなす行為〟と考えるのである。
マッキンタイアと同時代を生き、『人間にとって善とは何か』といった著作があるイギリスの倫理学者フィリッパ・フット(Philippa Foot、1920-2010)は、この根拠を人間の自然本性に求めた。
生のあり方
自然界を見渡すと、あらゆる動植物は、その種独自の機能を発揮することで、本来の「生のあり方」を実現し、種を繁栄させている。
たとえば、シカであれば俊敏さ、フクロウであれば暗視能力、オオカミであれば共同狩猟の能力をそれぞれ発揮することによって、生き延び、種が存続している。
フットによれば、それぞれの個体が「自己保存」と「種の繁栄」をめざし、その能力を発揮することが〝善い〟あり方なのである。
実践的合理性と理性的な意志
フットは、こうした自然界への見方を人間に当てはめて考えた。
動植物がめざす「自己保存」と「種の繁栄」は、人間においては「幸福」の追求に当たる。
一方、シカにとっての俊敏さのような種独自の機能は、人間においては「実践的合理性」に該当する。
そして、この「実践的合理性」は「理性的な意志」によって発揮される。
つまり、私たち人間は、「幸福」という目的を実現するために、各人が「理性的な意志」によって「実践的合理性」を発揮するが、そうしたあり方こそが人間本来の「生のあり方」であり、〝善い〟あり方なのだと、フットは唱えた。
トロッコ問題(路面電車問題)
ちなみに、フットは、「トロッコ問題」もしくは「路面電車問題」と呼ばれる著名な思考実験を提供している。
これは、〝ある人を助けるために他の人を犠牲にすることは許されるか?〟という倫理的なジレンマを考察するための問題で、応用倫理学や道徳心理学、神経科学などの分野において活発に議論されている。
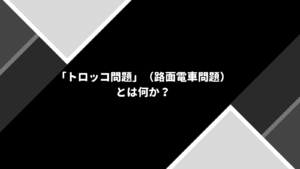
ハーストハウス
アンスコムやフットの哲学を引き継いだ哲学者・倫理学者の代表が、イギリスの哲学者・倫理学者ロザリンド・ハーストハウス(Rosalind Hursthouse、1943/11/10-)である。
ハーストハウスは、『徳倫理学について』のなかで、植物や動物にとっての〝善いあり方〟について考えることを通して、人間にとっての徳について考えた。
ハーストハウスによれば、たとえば、ある植物が「善」(エウダイモニア)であると言うことができるのは、その植物の葉や根、花びらといった各部分が充分に機能し、それによって、その植物自身が生存し、その植物の種が存続することができる場合に限られる。
また、ある動物が「善」だと言えるのは、その個体の各部分が充分に機能し、(1)その動物自身が属する種ならではのやり方で苦から逃れ、快を享受し、(2)それによって、その動物自身が生存し、(3)その動物の種が存続することができる場合に限られる。
さらに、群れて暮らす社会性のある動物にとって「善」だと言えるのは、上記(1)(2)(3)に加え、(4)その動物自身が、みずからが属する種にとって適切な役割を果たす場合に限られる。
このことについて、ハーストハウスは、〝針のないハチは、巣を機能させ、巣そのものを維持するという点で不完全である〟と言い表している。
ハーストハウスは、こうした植物や動物のあり方を人間に当てはめ、上記(1)(2)(3)(4)の目的を果たす性格特性こそが人間にとっての徳だと唱えた。
徳倫理学は、徳がどのようなものであるかについて明確化しなければ、何が正しい行為なのかを判断する客観的な根拠を持ちえないという批判と課題に直面していた。
ハーストハウスの学説は、こうした批判と課題に対して1つの〝答え〟を示したのであった。