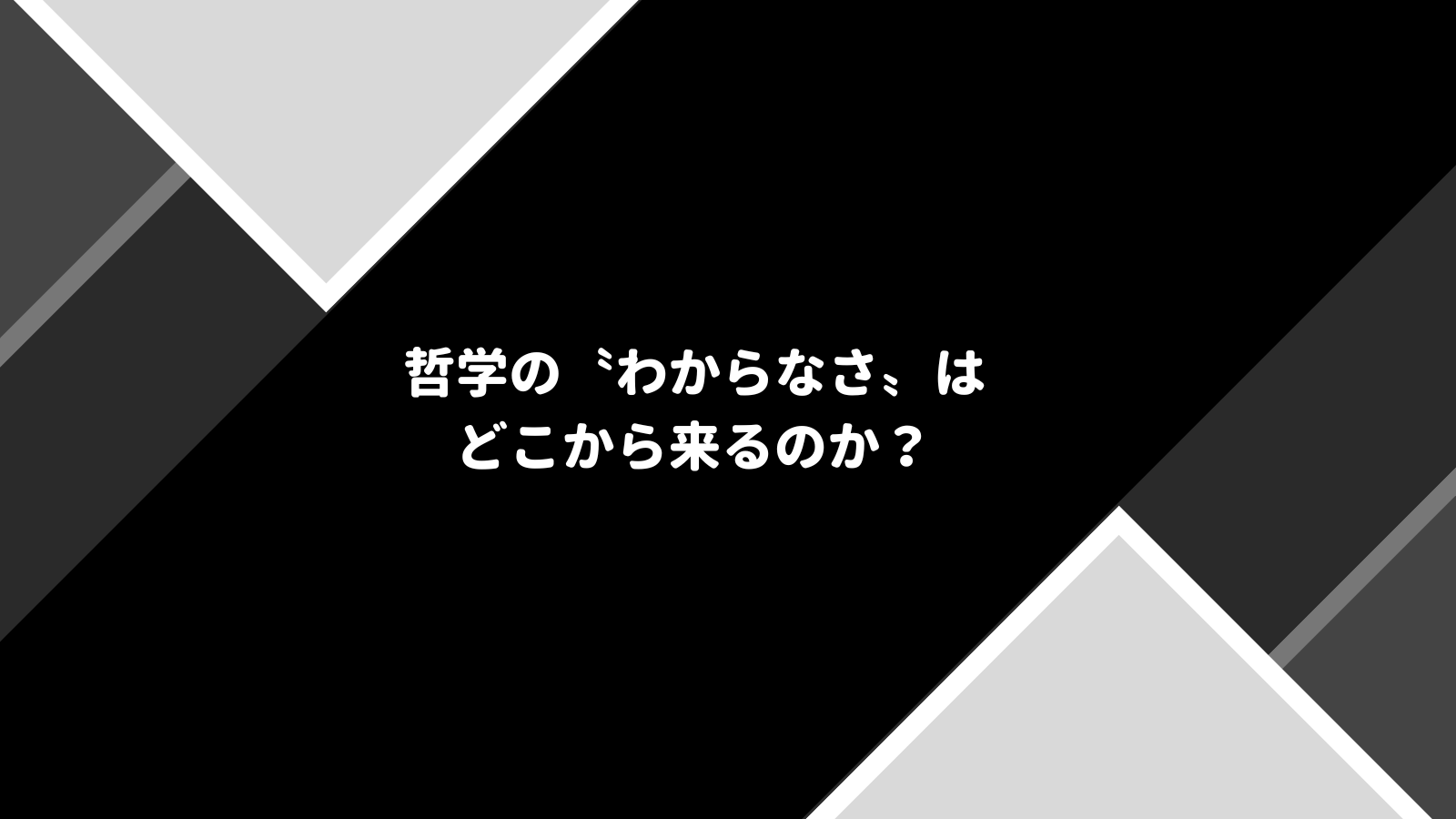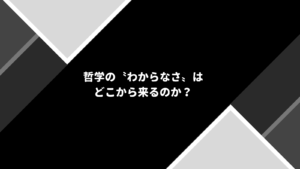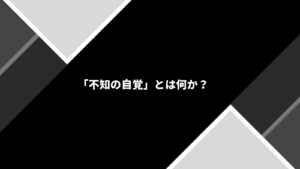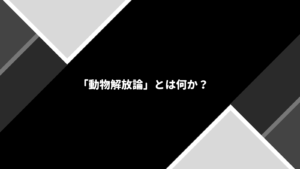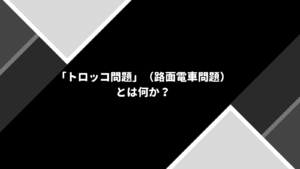ページ内にはアフィリエイトを利用したリンクが含まれています。
哲学はむずかしいが、なんとなく理解できる。でも……
「哲学って、わからない」
これは、ぼくが哲学に触れて、まもなくして感じたことである。
気をつけていただきたいのは、「哲学って、むずかしい」では決してないということだ。
哲学がむずかしいのは、むしろ当然である。
ぼくが最初に読んだのは、無謀にも、フッサールの『イデーン』とハイデガーの『存在と時間』だった。
当然、読み始めてすぐに、言葉の海の中に溺れていった。
それでも、意地になって読み進めた。
そして、完全に海の中へ沈んだ。
泳ぎも知らないのに、浮き輪なしで大洋のど真ん中へ泳ぎ出し、〝遭難〟したわけだ。
読んだという行為はあったものの、内容なんてさっぱり理解できなかった。
そこで、フッサールとハイデガーの入門書を何冊か読んだ。
なんとなく理解できたような気がした。
つまり、フッサールは、意識は必ず「何ものかについての意識」であり、意識に現出したものや直観されたものから認識が構成されていくプロセスを「本質直観」や「ノエシス―ノエマ」といった概念を用いて解明したのだった。
また、ハイデガーは、これまでの哲学は〝世界や事物はいかにして存在するか?〟という問いに答えようとしてきたが、実はそうした問いよりも重要なのは〝そもそも存在とは何か?〟〝人間とはどういう存在か?〟という問いのほうだと考え、その問いについて「死」「非本来性」といった概念を用いて答えようとしたのだった。
学校で数学の問題を解くように理解することは到底できなかったが、でも、彼らの考えたことの概略は、むずかしいながらもなんとなく理解できたのだった。
ところが、だ。
なんかしっくり腑に落ちないものがある。
フッサールやハイデガーが考えた内容はなんとか理解できるのだけれども、なんか〝わからない〟ものが残ったのだった。
この〝わからなさ〟の正体が、ぼくにはしばらくの間、つかめなかった。
〝わざわざ哲学する理由〟とは何か?
哲学に対する〝わからなさ〟を抱いたまま、ぼくはソクラテスやプラトン、デカルト、カント、ヘーゲルに入門していった。
〈みんな、けっこうムズカシイこと考えてたんだな。……でも、なんで、そんなこと考える必要があるわけ? 言ってることはなんとなく理解できるけど、別にそんなこと、考えなくたって生きていけるじゃん〉
……と、そこまで考えて「ん?」と思った。
〈これが〝わからなさ〟の理由?〉
そう、人は哲学なんて知らなくても生きていける。
考えることは誰でもしているが、哲学と呼ぶことができるほどに日夜考えている人は、そうはいないはずだ。
でも、人はふつうに生きていける。
なのに、〝わざわざ哲学する理由〟とは何だ?
その理由をわからずして哲学を学んでも、さらには、その理由を共有できなければ、哲学の上っ面(うわっつら)しかわからないんじゃないのか?
ぼくは、そう思ったのだった。
古代以来、哲学は〝世界のほんとうの姿〟を認識しようとしてきた。
世界が〝ほんとうは〟どういう姿をしているかを明らかにすることによって、世界に対してどのようにふるまえばいいのか?〟が導き出されると考えたからだろう。
このことが〝わざわざ哲学する理由〟の1つだと言えるかもしれない。
でも、まだ、それでは納得できない。
世界へのふるまい方がわかるとしても、やっぱり〝なんでそこまで考えるのか?〟という疑問は依然として残るからだ。
そこで、ぼくは、とりあえずこう考えた――
〝わざわざ哲学する理由〟は、哲学する本人のなかに、それぞれの形としてある。
〝世界のほんとうの姿を認識する〟という形式をとりながらも、哲学する当の本人が抱える、たとえば〝生きづらさ〟とか〝自分自身への居心地の悪さ〟とか〝社会への不適合感〟とかいった〝のっぴきならない問題を解消すること〟が、哲学する理由だ。
また、その〝のっぴきならなさ〟の度合いの強さが、〝わざわざ哲学する理由〟の強さになるのだ、と。
それを共有できないと、哲学はわからない。
ちょっと実存的っぽいが、思いつくことといえば、それしかなかった。
なので、「哲学の〝わからなさ〟はどこから来るのか?」という、この記事のタイトルへのとりあえずの答えは、こうなる――
こちら側が、対象の哲学者と同じような〝問題〟を抱えていないとか、その〝問題〟に共感できる共通の基盤を持っていない場合は、〝わからなさ〟を感じてしまう。
あるいは、同様の〝問題〟や共通の基盤を持っていたとしても、そのことへの自覚が低ければ、やはり〝わからなさ〟を感じてしまう。
ちょっとでも親近感をおぼえる哲学者に食らいついていくのが大事
ちなみに、ぼくは、ほとんどの哲学に〝わからなさ〟を感じている。
上っ面の理解はできても、たいてい〝わからなさ〟が残る。
ある哲学者が抱える〝問題〟を簡単に把握できるわけはないし、把握できたからといって〝問題〟にそうたやすく共感できるわけでもない。
でも、そんななかでも、必ず1人や2人、なんとなく親近感をおぼえる哲学者はいる。
そんなときは、自分と同類の匂いがする。
そうした哲学者が見つかれば、幸運である。
あとは、その哲学者に食らいつくのみだ。
そして、その哲学を味わい、批判してみる。
納得がいかないところは、自分ならどう考えるかと思考していく。
大切なのは、対象の哲学(者)のほうを大切にするのではなく、自分自身の思考のほうを大切にすることだ。
「この問題をヘーゲルならどう考えるか?」と考えること自体は問題ない(それが楽しいかどうかは別として)。
でも、その営みを「自分ならどう考えるか?」ということよりも価値あるものとして位置づけてはいけない。
あなたは決してヘーゲルではない。
他人の哲学の〝奴隷〟になってはいけない。
それが〝哲学を学ぶ〟〝哲学する〟ことなのだと、ぼくは思っているし、歴史に名を残した哲学者はみな、そうしてきたんじゃないかと思っている。