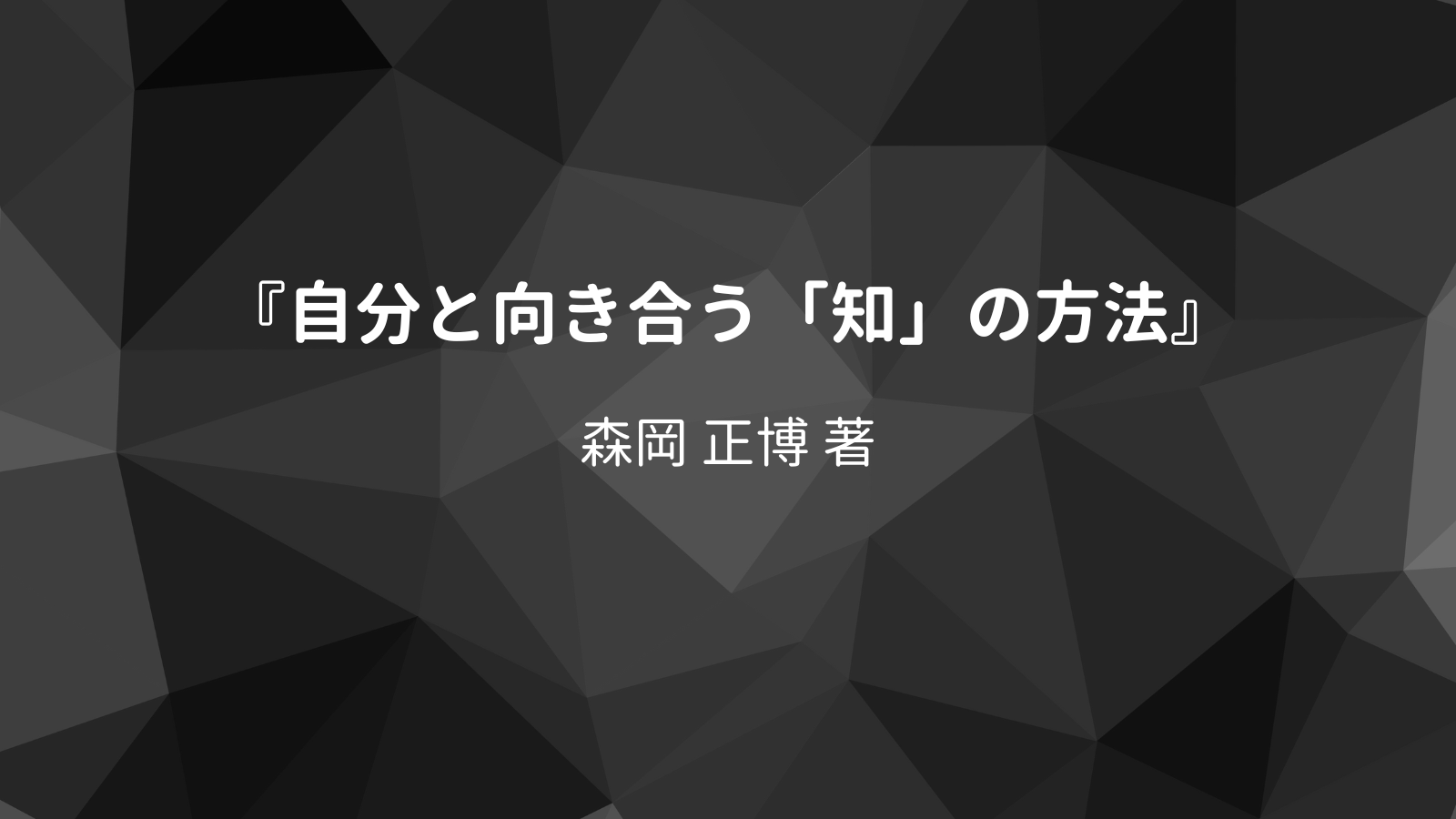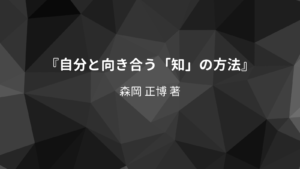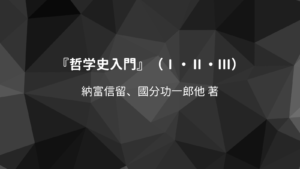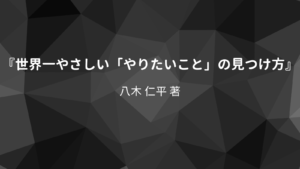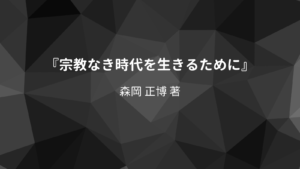ページ内にはアフィリエイトを利用したリンクが含まれています。
〝客観的〟な学術大会の発表。でも……
大学院に入学したての1992年、ぼくは、ある学術大会の運営の手伝いに駆り出されたことがある。
役回りは、発表者が持ち時間をオーバーしたら、ベルを鳴らすという係だ。
ところが、大会のプログラムを見て、ぼくは少しびっくりした。
発表のタイトルの大半が、揃いも揃って、「〇〇〇における△△△の□□□について」だったからだ。
たとえば、「中世キリスト教神学におけるアリストテレス哲学の影響について」といったような感じである。
それ以外のタイトルのつけ方はいけないかのような雰囲気すら感じさせるものであった。
発表の内容はというと、程度の差こそあれ、どの発表も〝客観的〟だった。
ぼくは指導教授から、「研究は客観的でなければいけない」と教わっていたが、それを地で行く発表のように思えた。
しかし、ほとんどの発表は、おもしろくなかった。
あるものごとや事象を傍観者の視点で見て、それを発表しているだけ。
発表の内容に発表者自身が存在しないので、発表に血が通っていない――
そのように感じられたのである。
当時、もしもそんなことを言っていたとしたら、まちがいなく指導教授に〝君は邪道だ〟と叱られていたはずだ。
もっとも、その2年後、ぼくの修士論文の論題は、みごとに「〇〇〇における△△△の□□□について」になっていたが……(苦笑)
「生命学」に出逢う
大学院は修士のみで修了した。
結婚するので職を得なければいけないという理由が第一だったが、博士後期課程へ進もうという意欲が湧かなかったのも大きな要因だ。
先の学術大会での違和感が、〈研究対象のなかに自分を置いてはいけない研究って、いったい誰のための研究なのか?〉という疑問になっていたからである。
数年後、そんな素朴な疑問への〝答え〟を知ることになる。
その〝答え〟が、『自分と向き合う「知」の方法』であった。
 |
当時は単行本だった本書が書店で平積みになっているのを、なんとなくタイトルに惹かれ、手に取り、パラパラとページをめくると、こんな記述が目に飛び込んできた――
いま必要なのは、いまここで生きている「私の生と死」との関係のなかで、自己について考え、社会について考え、世界について考えるような思想である。対象と自分とをけっして切り離さず、この自分がその対象に実際にどのようにかかわっているのかを、つねに考え続けるような思考方法。それが、これからの時代の思索の基本にならざるを得ない。それは、ものを考えることが、つねにそれを考えている自分自身の生き方へフィードバックするような、そういう思考方法である。私はそのようなものの考え方のことを「生命学」と呼んできた。
「第一章 自分と向き合う『知性』とは」
このフレーズを読んだ瞬間、ぼくの疑問に〝答え〟が与えられたような気がした。
そう感じ、即、購入した。
そして、丸2日かけ、読みふけった。
その間、仕事は手につかず。
というか、当時は書籍編集者だったので、企画を検討しているフリして読んでいた(笑)
〝自分を棚上げしないで考える〟――それが生命学
内容は、どストライクだった。
著者は、哲学者の森岡正博氏である。
本書『自分と向き合う「知」の方法』の刊行の2年前に起きたオウム真理教による「地下鉄サリン事件」が森岡正博氏に大きな衝撃と問題意識をもたらしたそうで、それが内容の核となっていた。
多くの評論家たちがオウムについて論評した。しかし、ほとんどの評論には、自分がひょっとしたらオウムに入っていたかもしれないという切実さが感じられなかった。自分のことを安全地帯の傍観者の位置において、遠くからオウムのことをあれこれ断罪していた。まるで、自分たちはこの事件にいっさい無関係であるかのような、そういう口ぶりが目立った。
「第一章 自分と向き合う『知性』とは」
森岡正博氏は、オウム事件が他人事とは思えなかったという。
「オウムは私だ」という地点からしか考えられなかったそうだ。
だから、「いまここで生きている自分のあり方を、けっして棚上げにしないような思想」と「『自分』というものを、みずからの思想のなかに巻き込む覚悟」が必要なのだと唱えるのである。
これが、森岡正博氏がものを考える際の基本スタンスとなっている。
たとえば、人種差別や女性差別などの問題。
考えるときは、差別問題そのものを傍観者的に突き詰めようとするだけでなく、同時に、「この私も差別に加担してきたのではないか、そしていままさに差別に加担しているのではないか」と自問自答し、自分自身をも突き詰めていかなければならないと主張する。
あるいは、環境問題や障害者問題。
たとえば環境問題を考えるとき、南北問題や環境破壊の構造を捉えることはとても大事なのだが、それと同時に、いまここで大量のエネルギーと資源を使って生活している私自身のことを考えなければならない。夏になればクーラーを入れて快適に生活をしている私のこと、私の職場のことを冷静に捉えなければならない。
「第一章 自分と向き合う『知性』とは」
たとえば障害者問題を考えるとき、障害者は社会のお荷物だから生まれてこないほうがいいという思想の不当さについて議論していくと同時に、「わが子の場合には五体満足な子が欲しい」とこころのどこかで思っている、この自分自身のことを思索へと上げてこないといけない。
客観的な研究は必要である。
しかし、それだけではなく、いやそれ以上に、対象とする問題のなかに自分自身を投げ入れて考えることが必要だ。
これからの時代は、これら2つを車の両輪として、ものごとを考えていかなければいけない――
ぼくは、森岡正博氏の主張をそう受け取った。
それにしても、ぼくは、このあたりまで読んで、自分を棚上げにしないで考えるというのは〝言うは易し〟で、精神的にはつらく、〝行なうは難し〟だと感じた。
当たり前の話であるが、人間には、自分にとって都合が悪いものからは目をそむけ、見たくないものは見ないようにする悪しき習性があるからだ。
この習性を手なずけながら、自分を巻き込んで考えていくのはキツいと思う。
ちょっとでも気を抜くと、いつのまにか安全地帯の傍観者的な視点〝のみ〟で考えてしまうはずだ。
それでも、森岡正博氏が、自分を巻き込んでまで考えていこうとする理由は何か?
私は、これらの問題を考え、そしてこの自分がどう生きていけばいいのかを考えるとき、自分のいのちというか、魂というか、そういうものがほんとうに生き生きとしてくるのを感じる。そういうことを考えて、自分の実際の生へと当てはめようとしてみるときに、胸の高鳴りを覚えて、「ああ生きている」って思う。そんなことを考えることは、実はとってもしんどいのだし、学習のつらいプロセスはいたるところにあるのだけれど、でも考える熱気の方がそれを上回る。
「第一章 自分と向き合う『知性』とは」
本書『自分と向き合う「知」の方法』では、こうした森岡正博氏のスタイル=生命学にもとづいて、教育、医療、福祉、ジェンダー、生と死、宗教などの問題が、数々の短編というスタイルで考察されている。
自分を棚上げにしないという哲学的思考のサンプルが明確に示されていて、真剣にものを考えてみたい人にはとても参考になるオススメの1冊だ。