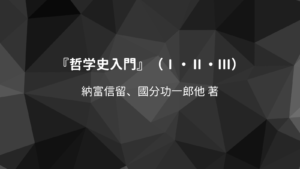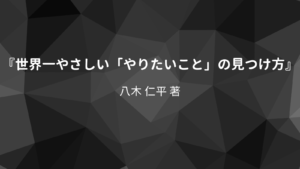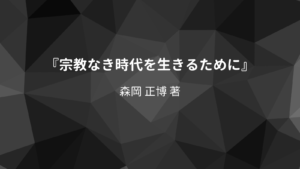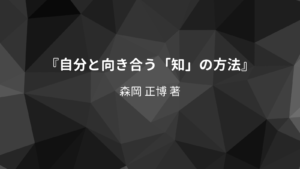ページ内にはアフィリエイトを利用したリンクが含まれています。
理念や理想の絶対視は不毛な争いを生む
21世紀になって、宗教や人種差別、所得格差などを背景とする価値観や考え方の対立が目立つようになってきた。
争点となっている問題に対して、〝自分はこう考える〟〝いや、オレの立場はこうだ〟という言い合いを越え、自分の正当性に固執し、〝まちがっている相手〟を(精神的、ときには物理的に)攻撃するような状況にすらなっている。
こうした攻撃的な言動にまでいたる人びとは、おそらく〝自分は正義、相手は不正義〟と考え、正義の側にいる自分が言ったりやったりしていることは善で、不正義の側にいる相手が言ったりやったりしていることは悪だと思っているはずだ。
だから、〝勧善懲悪のヒーロー〟よろしく、〝悪〟を打ち負かしてもよいと考えるのである。
では、なぜ、そう考えるにいたってしまうのか?
その最大の理由は、〝世界には(不変の)正しさや善がすでに存在し、自分はそれらを知っている〟という理念や理想の(意識せざる)絶対視が根本にあるからだ。
ぼくは、そう考える。
つまり、〝世界はこういうふうに存在している〟〝人間存在とはこういうものである〟〝これが生きる意味である〟〝善悪の基準はこうである〟……というような、世界や人間のあり方や意味がすでに決まっていて(宗教であれば、それらが神によって決められていて)、それらを知っている自分こそが正しく善く生きることができるという盲信である。
だから、双方とも、〝自分のほうがまちがっているかもしれない〟とは決して思わない。
それどころか、自分たちの理念や理想を世の中に広め、〝まちがっている人びと〟を減らさなければいけないという使命感すら抱いていたりする。
そのため、妥協点は見出せず、争いになるわけだ。
不毛である。
しかし、こうした争いは、大昔から見られるほどに普遍的である。
宗教戦争などは最たる例だ。
では、どう解決すればいいのか?
「主観と客観の一致」から「生世界の本質の解明」へ
その解決の可能性を哲学の原理として示そうとしているのが、『哲学とは何か』である。
 |
著者は、竹田青嗣(たけだ・せいじ)氏である。
氏は、フッサールの現象学を中心に、〝哲学とは何をする営みか?〟について長年考えつづけてきた。
『現象学入門』『現代思想の冒険』『超解読!はじめてのフッサール『現象学の理念』』など、数多くの著作がある。
本書『哲学とは何か』には、次のような記述がある――
こうした哲学の思考方法を以下に総括できる。ある問題について、さまざまな考えから、これについては誰もがこう考えざるをえない、という考え方の道を探して進むという方法である、と。宗教の世界説明は任意の「物語」によって作られる。しかし哲学はこの方法を排して、「誰にとってもこう考えるほかない」という方法、つまり普遍的な共通了解をめがける思考の方法なのである。
「序 哲学の方法と功績」
「『誰にとってもこう考えるほかない』という方法」というものがあれば、とっくに争いはなくなっているのではないか?
そう疑問に思われたかもしれない。
しかし、この前提には、根本的な思考の転換がある。
本書『哲学とは何か』によれば、哲学の世界では、大きな考え方の対立が続いてきたという。
「本体論」vs「相対主義=懐疑論」の対立である。
「本体論」とは、「世界それ自体の存在という観念」にもとづく考え方のことだ。
「本体論」では、人間のあり方に関わりなく存在する世界を、人間がいかに正しく言い当てるか=認識するかが問題となる。
つまり、対象を正しく認識すること=「主観と客観の一致」をめざす。
一方、「相対主義=懐疑論」は、〝存在は証明できず、存在したとしても認識できず、認識されたとしても言葉にできない〟(「ゴルギアス・テーゼ」)という考えを基本スタンスとする。
「主観と客観の一致」は不可能だというわけだ。
古代ギリシアのソフィストや近代のヒュームが、その代表である。
この対立は、現代まで続いた。
19世紀後半にドイツ観念論がすたれ、「唯一の正しい世界観」を唱えるマルクス主義が登場するも、大きな矛盾を露呈して崩壊しはじめると、ポストモダン思想という相対主義が登場し、主役の座についた。
古代以来の対立は「正しい世界認識」をめぐっており、「正しい世界認識」を問題にする限り、議論は堂々めぐりになる。
ニーチェとフッサールは、〝人間のあり方に関わりなく存在する世界〟という意味での「客観」という概念を取り払った。
つまり、対象を正しく認識すること=「主観と客観の一致」という問題そのものを「解体」したのだ。
こうしたニーチェとフッサールの根本的な思考の転換の意義を、竹田青嗣氏は、次のように述べている――
まず、ニーチェはいう。真に存在するのは「生成」としての生世界のみであり、本体としての世界はどこにも「存在しえない」と。しかしこれは「世界は存在しない」というゴルギアス・テーゼに帰着しない。現象学の観点からは、世界の存在は認識されないというにすぎず、われわれにとって、むしろその現実存在は本質的に「不可疑」なのである。
「第四章 『言語の謎』と『存在の謎』の解明」
ゴルギアスがいうように世界の存在は証明もされず、それゆえ認識されえない。しかしその理由は、それが認識の対象ではなく、想定としての対象だからである。しかし同時に、われわれは、生の世界を可能にしている「原存在」としての世界を決して疑うことができない。そしてこの世界の存在の不可疑性は万人にとって普遍的な信憑構造であって、どんな相対主義=懐疑論も論駁できない。たとえ、どんな頑固な懐疑論者であれ、実際は世界の存在を信じているし、この信は任意の信ではなく不可疑の構造としての信なのである。……
そして、この転換によって、哲学の問いの形も転換すると、竹田青嗣氏は言う――
最後に一つだけつけ加えねばならないことがある。世界における何らかの「原存在」の存在は、われわれの「生世界」の根拠として絶対的な不可疑性をもつ。つまり、「自然世界の実在」は人間にとって完全に不可疑なのである。こうして、われわれが「生世界」を生きているという現実自体が必然的に要請する、世界の存在についての根本的な想定―信憑を、私は「原存在信憑」と呼ぶ。
「第四章 『言語の謎』と『存在の謎』の解明」
哲学における「存在の謎」、すなわち、世界の全体はどうなっているか、世界の存在理由が何であるか、また、そもそもなぜ世界が存在するのか、といった問いは、世界の「本体」はそもそも認識の対象ではないが、しかし世界の現実存在はわれわれにとって不可疑であるという「原存在信憑」の概念によって終焉すべきものとなる。哲学が問うべきは、「世界の本体」ではなく、この観念を必然的に生み出す人間の「生の世界」の本質とは何かという問いであることが明らかになるからである。
「普遍認識」の可能性をさぐる
このあと、竹田青嗣氏は、自然科学によって数値化できる「事物の領域」(事実の領域)と、数値化できない意味や価値の「本質の領域」(人文領域)を区別し、「本質の領域」における「普遍認識」=〝人間や社会に関わる問いに関する誰もが納得できる認識〟を探求している。
そのための武器として使われるのが、フッサール現象学の「本質観取」という概念だ。
「本質観取」とは、〝あるものごとが人間の生にとってどのような普遍的な意味=本質をもつか、人びとの経験の内側を洞察すること〟である。
そして、この「本質観取」によって、医療、精神分析、倫理学、社会理論などの領域を分析し、「普遍認識」の可能性を探求していく。
その詳細は、ぜひ本書『哲学とは何か』を読んで確認してほしいが、主観/客観図式から抜け切れないぼくにとって、目からウロコの記述がいくつもあった。
そして、説得的だったのは、人文領域の各分野において、なぜ理念や理想の対立を克服できないのかという理由についてである。
また、社会が人間にとってもつ意味=本質を考えるにあたって、何を動機とし、何をめざして、いかなる方法で考えていけばいいのか、という道筋についてである。
なぜ理念や理想の対立が起きるのかを知り、社会の本質について考える人が増えていけば、おのずと争いは減っていくのではないか。
なぜなら、そのことを知り、考えることが、社会問題、とりわけ資本主義の問題(竹田青嗣氏は、資本主義における格差の拡大への対応を、現代哲学の最大の仕事だと考えている)を克服する道へとつながっているからである。
あなたが、とりわけ社会問題や資本主義に関心があるなら、ぜひ本書『哲学とは何か』を読んでみてほしい。
きっと大きなヒントを得られるはずだ。