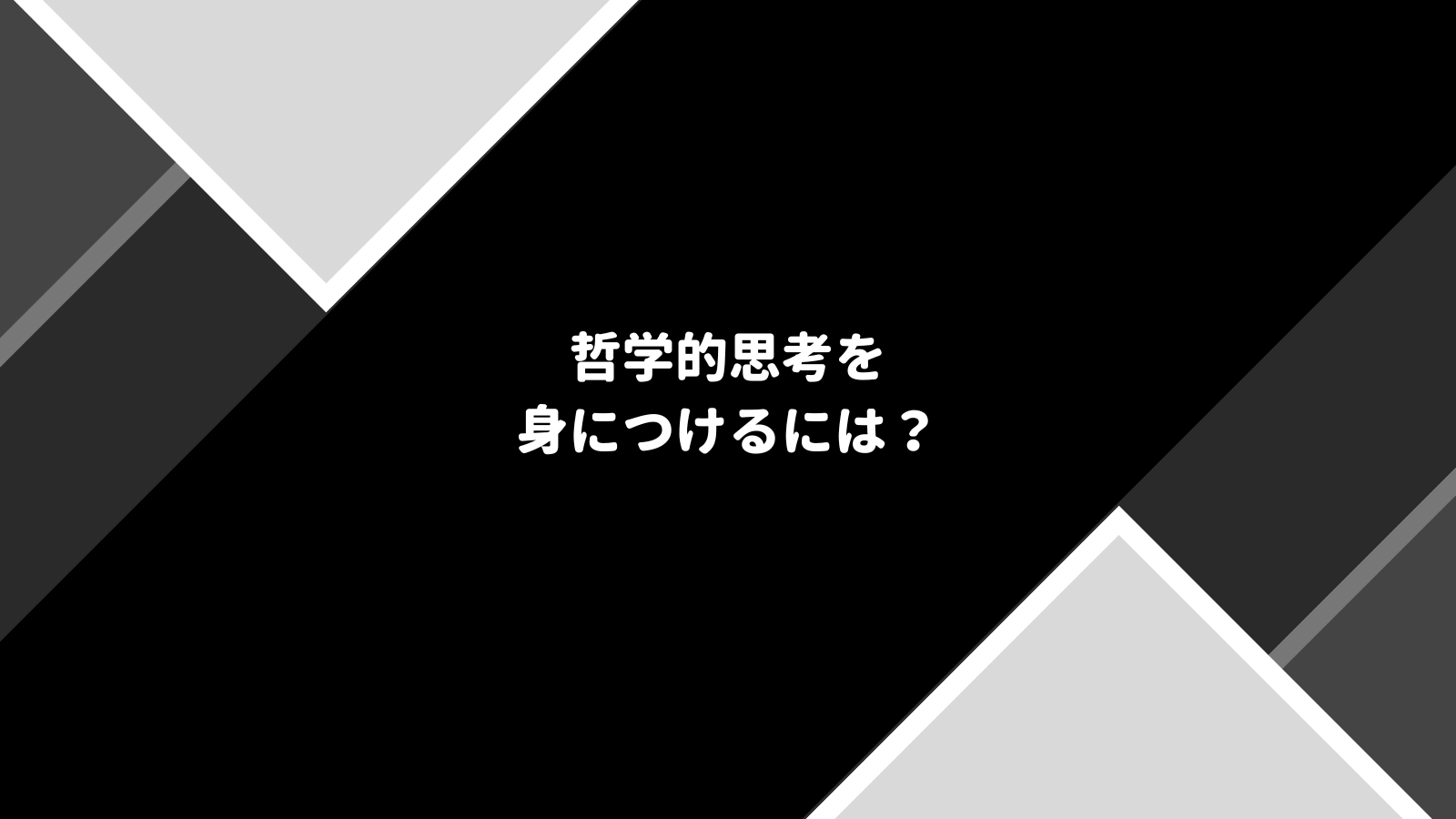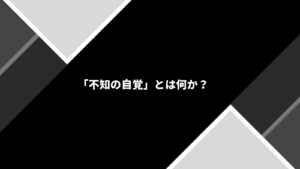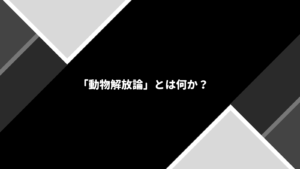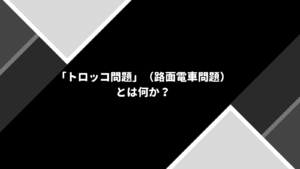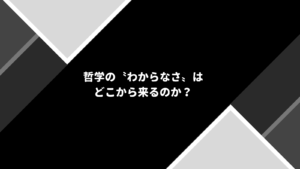ページ内にはアフィリエイトを利用したリンクが含まれています。
哲学の問いとは?
大学には「哲学」という科目がある。
哲学科に入学したのではなくても、いわゆる一般教育科目のなかの1科目として「哲学」はある。
でも、高校で「倫理」を選択した学生ならまだしも、他のたいていの学生からは、〈テツガク? 何するの?〉と思われているのではなかろうか?
政治学や経済学、物理学、医学などとは違って、「哲学」という科目名からは、その中身がぜんぜん見えてこないからだ。
では、「哲学」とは何をする学問か?
哲学者の土屋賢二氏は、『ツチヤ教授の哲学講義』の「はじめに」のなかで、こう言っている――
自分で考えてみて納得するかどうかが哲学のすべてである。
実に簡潔な説明だ。
では、何について考えるのか?
それは、ひとことで言えば、自分の頭にこびりついて離れない問いだ。
たとえば――
- なぜ、ぼく(わたし)はここに存在しているのか?
- ぼく(わたし)はいかに生きるべきか?
- この社会はどうあるべきか?
- 死とはどのようなものか?
……などなど。
こうした哲学の問いについて、哲学者の永井均氏は、『〈子ども〉のための哲学』のなかで、哲学を「子どもの哲学」「青年の哲学」「大人の哲学」「老人の哲学」の4つのありかたに分けたうえで、こう語っている――
子どもの哲学の根本問題は、存在である。森羅万象が現にこうある、というそのことが不思議で、納得がいかないのだ。ここでは問いは、どうしたらよいのか、ではなく、どうなっているか、というかたちをとる。人生や自己が問題になる場合でも、それは変わらない。存在論はもちろん、認識論や意味論、そして科学哲学や言語哲学のすべての根底には、子どもの哲学がある。(中略)
「問いの前に 〈子ども〉のための哲学とは?」
青年の哲学の根本問題は、人生である。つまり、生き方の問題だ。いかに生きるべきか――このひとことに青年の問いは要約される。(中略)
大人の哲学の最重要課題は、世の中のしくみをどうしたらよいか、にある。生き方や人生の意味とは別の、社会の中での行為の決定の仕方が問題になる。(中略)
老人の哲学の究極主題は、死であり、無である。それを通じてもう一度、子ども時代の主題であった存在が、問題になるだろう。(中略)
青年の哲学、大人の哲学、老人の哲学は、それぞれ、文学、思想、宗教で代用できるが、子どもの哲学には代用がきかない。子どもの哲学こそが最も哲学らしい哲学である理由がそこにある。そこにこそ、何ものにもとらわれない純粋な疑問と純粋な思考の原型があるからだ。
なお、永井均氏が言う「子ども」「青年」「大人」「老人」というのは、もちろん実際の年齢区分のことではない。
哲学的な問い、ここではとりわけ「子どもの哲学」の特徴を明確化するための比喩である。
だから、文学や思想や宗教に代用できない子どもの哲学の問いが、他の哲学の問いにくらべて、より根源的ではあるだろうが、決してより〝高級〟なわけではない。
哲学的思考はどうしたら身につくか?
このように、哲学の問いは種類分けできるのだが、問いについて考えるにあたっては、すべての問いについて共通して言えることがある。
それは、先の土屋賢二氏の言葉をぼくなりにアレンジすれば、〝言葉だけを頼りに、自分が納得するまで考える〟ということだ。
でも、そうは言われても、いったいどのように考えたらいいのか、まるでわからないというのがふつうであろう。
そこで、〝哲学的に考えるとはこういうことだ〟というサンプルが必要になる。
そのサンプルを読んで、哲学的思考がどんなものかを自分なりにつかんでいくのだ。
ほんとうなら、過去の哲学者の著作を何冊か読むのがいちばんいい。
でも、それらの著作は、まずまちがいなく難解である。
予備知識なしに読むと、過去のぼくのように、120%〝遭難〟する(汗)
ヘタをすると、哲学が大嫌いになる(大汗)
ぼくは、かろうじてまぬかれたが……。
だから、そうならないように(別にそうなっても生活が困るわけではまるでないので、それでいいのだが……)、前もって哲学的思考を入門者向けにていねいに手ほどきした著作を読むのが安全だ。
そこで、以下に、比較的入手しやすいオススメの入門書を3冊紹介する。
参考にしてほしい。
オススメの入門書
『〈子ども〉のための哲学』(永井均 著)
 |
まず1冊めは、『〈子ども〉のための哲学』である。
『子どものための哲学対話』『翔太と猫のインサイトの夏休み』『倫理とは何か』などの著作がある永井均氏が、子どものころからいだきつづけてきた問い――「なぜぼくは存在するのか」(独我論)「なぜ悪いことをしてはいけないのか」(道徳の根拠)について哲学している。
永井氏自身が哲学するプロセスをそのまま書きしるしているので、哲学的思考がどういうものかがよく理解できる。
哲学に関心がある中学生以上なら充分に読みこなせるはずだ。
永井均氏が考える哲学とは、誰かの役に立つという目的で行うものでは決してなく、徹頭徹尾、自分自身の疑問を考え抜くためだけに行う「利己的」ないとなみであるということがはっきりとわかる。
『哲学のきほん』(ゲルハルト・エルンスト 著)
 |
2冊めは、『哲学のきほん』である。
著者は、巻末の「解説 二〇世紀的思考法からの脱却」によると、「いわゆる『分析哲学』を専門領域とする新進気鋭のドイツの哲学者」ゲルハルト・エルンスト氏(Gerhard Ernst)である。
原題はドイツ語で「Denken wie ein Philosoph」。
訳すと、「哲学者のように考える」。
つまり、哲学者が何をどのように考えるのか、読者が追体験できるように書かれているのが特徴だ。
取り上げられている問いは、7つだ――
「どう生きていくか?」
「他人とどう生きていくか?」
「道徳にはどれほどの客観性があるのか?」
「何を知ることができるのか?」
「世界には何が存在するのか?」
「哲学とは何か?」
「哲学は何のためにあるのか?」
「哲学者」と「読者」の対話形式(話し言葉)になっているので、読みやすい。
『哲学ってどんなこと?』(トマス・ネーゲル 著)
 |
3冊めは、『哲学ってどんなこと?』である。
著者は、1993年2月に書かれた「訳者あとがき」によると、「英米の哲学界で現在最も注目されている哲学者の一人」トマス・ネーゲル氏(Thomas Nagel、1937/7/4-)である。
取り上げられている問いは、9つだ――
「私たちの心を超えた世界を知ることができるのか」
「他人の心を知ることができるのか」
「心と脳の関係はどのようなものか」
「いかにして言語は可能になるのか」
「私たちは自由意志をもっているのか」
「道徳の基礎はどのようなものか」
「どのような不平等は正しくないのか」
「死とはどのようなものか」
「人生には意味があるのか」
これらの問いについて、その始点から直接考えるプロセスを、読者に語りかけるように書きつづり、「あなたが自分自身で思い悩むことができるように」(「はじめに」)手ほどきしている。
なお、副題に「とっても短い哲学入門」とあるように、140ページそこそこの小著である。