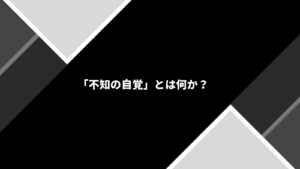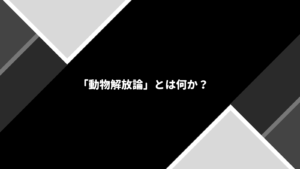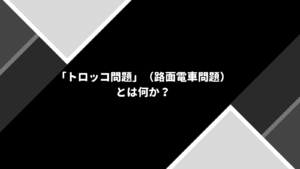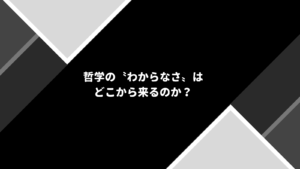ページ内にはアフィリエイトを利用したリンクが含まれています。
入門書は実は難解
大学の一般教育科目の「哲学」や、哲学科などの「哲学史」といった科目では、西洋哲学史を概観することが少なくない。
その場合のテキストは、「西洋哲学史概論」みたいなタイトルの、担当教員が執筆した(もしくは執筆に関わった)書籍を買わされることが少なくない。
ぼくが大学生のころ(1980年代後半)は、担当教員によっては、自分の書籍や教材を買わないと単位がもらえないということもあった(怒)
こうした授業に使われるテキストの多くは、読んでいて眠くなる。
その理由の1つは、〝入門〟と称しているにもかかわらず、記述が硬くて難解だからだ。
著者たちはふだん同業者向けに論文を書いている人たちで、一般読者向けに書くことに慣れていない。
だから、入門書的な本なのに、たとえば「自然的事物に代わって意識内の観念が直接の対象となる」なんていう文章が平気で出てくる。
著者としては、これでも平易に書いたつもりかもしれない。
それに、哲学は言葉だけが頼りで、言葉の使い方に神経質だから、仕方ないのかもしれない。
が、〈それにしたって他に言い方があるだろ〉と思ってしまう。
せめて「哲学が直接の対象とするものは、自然に存在するものから意識のなかの観念に代わった」ぐらいの表現にできないものだろうか。
ぼくがこのサイトで公開している「西洋哲学史と倫理学の基礎知識」では、そのへんのところを(どこまでできたかはわからないが)意識して書いたので、ぜひ参考にしてみてください。
入門書は没個性
入門書を読んでいて眠くなるもう1つの理由は、没個性なことにある。
西洋哲学は、紀元前7世紀のタレスに始まるとされる。
だから、その長~い歴史の描き方は、視点のとり方によっていろいろあるはずだ。
なのに、科目指定のテキストの多くは、〝客観性〟を重視しているので、「自分はこうとらえる」的な独自性が感じられない。
まずは、初学者には偏りのない見方を提供しようという意図なのだろうが、無味乾燥でおもしろくないため、のっけから〝客観的〟な入門書を読ませても、〈哲学はつまらない〉という逆効果を生んでしまうように思われる。
最初は、記述が平易で独自の視点をそなえた、読んでいて眠くならない(眠くなりにくい)入門書を読むほうが、哲学に興味をもってもらいやすいのではなかろうか。
なにごとも興味をもつところから始まるのだから。
オススメの入門書
『ヨーロッパ思想入門』
 |
著者は、『ギリシア哲学入門』『増補 ソクラテス』『よく生きる』などの著作がある岩田靖夫氏である。
本書『ヨーロッパ思想入門』のなかで岩田靖夫氏は、西洋哲学史の2大源流である古代ギリシアの思想とキリスト教(旧約聖書、新約聖書)の思想をていねいに解説し、そこからどのように近現代の哲学へと展開していったのか語っている。
西洋哲学とキリスト教の関係は深いのに、キリスト教に言及する入門書が少ないなか、本書『ヨーロッパ思想入門』は貴重だ。
西洋哲学史全般をとらえるための視点が養える。
これだけの質をそなえていて、中高生向けとは驚きである。
とにかく最初に読んでほしい。
『はじめての哲学史』
 |
本書『はじめての哲学史』の編著者は、『現象学入門』『プラトン入門』『哲学とは何か』など数多くの著作がある竹田青嗣(たけだ・せいじ)氏と、『哲学の練習問題』『集中講義 これが哲学!』『哲学は対話する』などの著作がある西研氏である。
古代から現代にいたる哲学者たちが、それぞれ、どういう時代状況のもと、何を問題とし、どう考えたかという視点にこだわって、その思考の〝型〟をシンプルに示している点で、他の入門書より秀逸である。
また、それでいて、中学生でもスラスラ読めるくらいに平易な文章である。
なお、著者たちの方法論はフッサールの現象学の独自の解釈にもとづいていて、終章の「むすび」で、その可能性を語っているのも特徴である。